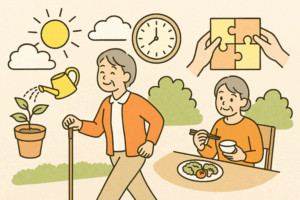座りっぱなしは危険!“座りすぎリスク”を減らす方法
座りっぱなしは危険!“座りすぎリスク”を減らす方法
在宅ワークや長時間のデスクワークが当たり前になると、1日で座っている時間が8〜10時間になる人も珍しくありません。問題なのは「合計の時間」以上に、何十分も連続して動かないことです。連続座位が続くと脚の血流が落ち、代謝が下がり、むくみ・腰痛・肩こりに加えて、糖尿病や心血管系のリスクも高まりやすくなります。ここでは、運動が苦手でもできる“立つ・動くの仕組み化”を紹介します。
1. 毎時1分立つ――最も効果が高いミニ習慣
1時間に1回、たった1分立つだけで、下肢の血流が回復し、エネルギー消費もわずかに上がります。スマホやPCにリマインダーを入れ、「通知が鳴ったら立つ」を自動化しましょう。立ったら、足首回し・ふくらはぎの上下運動・胸を開くストレッチをセットで行うと、全身の巡りがさらに良くなります。会議中で立てないときは、終了後に“2分補填”します。
2. 作業50分→回復10分のリズム
長時間座っていると、姿勢が前のめりになり、首・肩・腰に負担が集中します。これを防ぐには「50分集中→10分回復」というリズムにしてしまうのが一番シンプルです。回復の10分では、立ち歩き・家事1セット・階段上り下り・目を休める・白湯を飲むなど、座位を中断する行動を入れます。これを午前2回・午後2回やるだけで、1日の総立位時間が大きく増えます。
3. ワークスペースを“動きたくなる”ように変える
- 飲み物はあえて遠くに置く:机に置かないことで、立つ回数を強制的に増やす。
- 昇降デスクや簡易スタンドを導入:1日のうち20〜30%だけでも立ち作業にすると、腰やお腹周りがラクになります。
- イスと画面の高さを調整:膝が90度、骨盤はやや前傾、画面の上端が目の高さ。これで猫背時間を減らします。
4. 通勤・会議・休憩でも“ちょい動き”を積む
- 電車やバスでは1区間だけ立つ、または一駅手前で降りて歩く。
- オンライン会議は立って参加。カメラをオフにできる場面はその場歩き。
- 昼食後は早歩き5分。食後高血糖を抑え、午後の眠気も軽くなります。
5. 3週間で定着させるロードマップ
- 1週目:スマホにスタンド通知。飲み物を遠くに。1日の歩数を把握(今の基準値を知る)。
- 2週目:50/10リズムを平日に実行。オンライン会議を1日1回は立ちで参加。
- 3週目:立ち作業比率を20〜30%に。階段・1駅歩き・昼食後の早歩きを追加し、歩数の週平均を+500〜1000に。
6. よくある悩みと対処
- 「会議が長くて立てない」→会議後に2〜3分のストレッチ補填。足首・股関節を優先。
- 「立つと仕事に戻れない」→立つ行動をタスク境界に置き、再開するToDoをメモしてから立つ。
- 「腰がすでに痛い」→座面を高め&お尻の後ろにタオルで骨盤を立てる。立ちすぎも腰にくるので“こまめに姿勢を変える”ほうを優先。
まとめ:座りすぎ対策は“たくさん運動する”より“細かく中断する”が正解です。毎時1分の立ち上がりと50/10リズム、通勤・会議でのちょい動き、この3つを3週間回せば、むくみ・腰の重さ・午後のぼんやりがはっきり軽くなります。